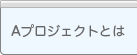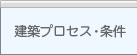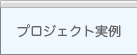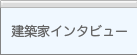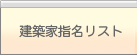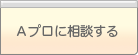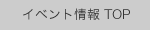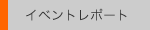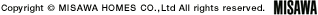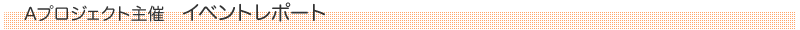
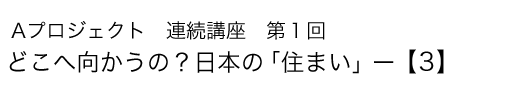
 ヴォーリズ建築の素晴らしさ
ヴォーリズ建築の素晴らしさ司会
共同体についてのお話がかなり出てきましたが、たとえば、集合住宅はこうあるべきとか、具体的なイメージはもたれていますか。
内田
あるべきというのはあまりないんですけど……この間、白川郷へ行って、合掌造りを見てきたんですが、あそこは十数人の人たちが一緒に住んでいるわけですよね。全体的にプライベートスペースが非常に狭いんです。でも、パブリックな場所を微妙に仕切ったりして、運用によって公共性と私(わたくし)性がアナログ的にひとつの場所で変わっていく。襖を閉めるとプライベートな空間ができる、襖を取り除くと宴会場にもなる。そういうふうにプライベートな空間が固定的に出来ているんじゃなくて、機能的に切り替わるかたちで確保されている。そういう工夫に感心しましたね。限られた空間の中にたくさんの人間が住むためには経験的に蓄積された、洗練されたノウハウがあるというのを、白川郷に行って感じましたね。
それと日本で見てていいと思う空間には、必ず暗がりがありますね。建物の大きさそのものに限界がある場合に、どうやってプライベートな空間を確保するかというときに、窪みとか暗がりとか、「よくわからない空間」をそこここに仕掛けておくんですね。そういう「何に使うのか一義的に決まっていない空間」が所々にあると、空間に濃淡とかリズムが出来る。この会場のように、全部均質的に出来ている場合は「ここからここまでがプライベートな空間です」っていう具合に仕切りを作るしかないけれど、伝統的な建築の場合では、私性というのが、「凹み」とか、通常の動線には属していないデッドスペースとか、隠し部屋とか、隠し階段とか、そういう仕掛けで確保されている。そういうのって、昔の武家屋敷とかを見るとよくあるじゃないですか。
それと、僕が今通っている神戸女学院大学のヴォーリズが設計した建物なんですけれど、これなんか見ていると、凹みとか窪みとか隠し階段とか隠し部屋とかが本当にこまめに仕掛けてあるんです。これは学校建築としては極めて正しい作り込み方だと思うんです。公共の空間のはずなんけれど、所々になんだかよくわからない空間がある。それを発見した学生が、「これはなんなんだろう?」と考える。その使い方を自分で考えて、じゃあ、私はこうやって使おうと考えると、その瞬間に公共空間がある種の私性を帯びるわけです。そこがプライベートな意味を帯びる。

それと日本で見てていいと思う空間には、必ず暗がりがありますね。建物の大きさそのものに限界がある場合に、どうやってプライベートな空間を確保するかというときに、窪みとか暗がりとか、「よくわからない空間」をそこここに仕掛けておくんですね。そういう「何に使うのか一義的に決まっていない空間」が所々にあると、空間に濃淡とかリズムが出来る。この会場のように、全部均質的に出来ている場合は「ここからここまでがプライベートな空間です」っていう具合に仕切りを作るしかないけれど、伝統的な建築の場合では、私性というのが、「凹み」とか、通常の動線には属していないデッドスペースとか、隠し部屋とか、隠し階段とか、そういう仕掛けで確保されている。そういうのって、昔の武家屋敷とかを見るとよくあるじゃないですか。
それと、僕が今通っている神戸女学院大学のヴォーリズが設計した建物なんですけれど、これなんか見ていると、凹みとか窪みとか隠し階段とか隠し部屋とかが本当にこまめに仕掛けてあるんです。これは学校建築としては極めて正しい作り込み方だと思うんです。公共の空間のはずなんけれど、所々になんだかよくわからない空間がある。それを発見した学生が、「これはなんなんだろう?」と考える。その使い方を自分で考えて、じゃあ、私はこうやって使おうと考えると、その瞬間に公共空間がある種の私性を帯びるわけです。そこがプライベートな意味を帯びる。

五十嵐
なるほど。それぞれ違うカスタマイズをしていくような関係性が無尽蔵に発生しうるわけですね。
内田
そうですね。ヴォーリズの設計した中庭にはいくつか道があってどれかを選ばないとならないんですけど、とにかく選択肢が多い。毎週会議があるので、同じ曜日の同じ時間に、僕は図書館本館から総務館という建物に移動するんですけれど、そのときにどのルートで行こうか選択することができる。雨の日は建物の中を歩くけれども、春は桜の木の下を通って行くし、秋は紅葉の木の横を通るし、夏は噴水の横を通る。季節ごとに、時間ごとに最適動線が変わる。そうすると、ふつうの中庭で、ただの道なんだけれども、やっぱりカスタマイズされるわけです。ここは私の学校の、私の中庭の、私の道なんだという気分になってくる。なんだか急にその空間が親密なものになってくる。動線というか選択肢が限定されていなくて、「You have the choice」という、そういう感じで使用者に提供されていると急に空間が親しみを帯びてくるってこと、あるじゃないですか。
五十嵐
建築家の青木淳さんという方が、『原っぱと遊園地』という本の中で似たような議論を語っていて、遊園地というモデルは、ここではこういうふうに振る舞いなさいという、所作というか動作までがあらかじめ一義的に決定された場所であるのに対して、原っぱの空間モデルは、今言ったような、完全に定義されていないがゆえに、ぼんやりあるんだけれども、来る人が、そこでそれぞれの使い方を導き出すっていう言い方をされています。
内田
ヴォーリズの建築というのは、ふつうの建築評論家みたいな人は、その外観だけを見て、審美的な意味で奇麗ですねって言って終わりなんです。でもこの建物の本性は使ってみないとわからない。僕はヴォーリズの校舎が「学びの比喩」になっているという話をよくするんですけど、いろんな隠し階段とか隠し扉があるんです。思いがけないところに螺旋階段があって、それを登ってゆくと窓がある。そこからは他のどの場所からも見えないような鮮やかな風景が切り取られて見える。それが好奇心を持ったことに対するご褒美なんですよ。自分の手でドアノブを開けて、自分の足で廊下を進み、階段を登っていくと、自分だけしか見たことない風景が待っていますよって。素敵だと思いませんか、好奇心に駆られて見知らぬ空間に踏み込むと、そこから誰も見たことのないような広々とした景色が見える場所にたどりつくんです。大学の校舎として、こんな教育的な設計思想ってないんじゃないかと思うんです。
五十嵐
そういう意味では、校舎で日々、建築について鍛えられていたみたいなところが実はあったのかも知れないですね。
内田
そうですね。20年いましたからね。あの校舎の中に。でも、一度、けっこうショックなことがあって。大学に来て何年目かに、あるシンクタンクが入って来て、大学の再建計画を1年間かけてつくっていった。そのときにヒアリングをされたんですが、そのときに向うの調査員が「この建物は無価値ですから」って言うんですよ。「築60年でしょ、雨漏りもするし、耐震も駄目だし。こんな建物を持っているってのは、ドブに金を捨てるみたいなもんです」って。僕はそれを聞いて本当にびっくりした。「あなた方はこの建物の価値がわからないの?」って。でも、彼らは坪単価とか維持費とか、そういう数値でしか建物の価値を量ることができなかったんです。そこにいると「わくわくする」とか、四季の変化がはっきり体感されるなんていうことを彼らはまったく勘定に入れないんです。でも、校舎の価値を考量する基準は、費用対効果なんかじゃなくて、その中にいると、知的なアクティヴィティが高まるかどうかっていうことでしょう。それ以外に校舎の価値を量る基準はないですよ。


五十嵐
しかし、資本主義的に数字に還元すると、校舎も消費財であり、そういう査定になってしまう…。
内田
悪いけど、よその大学の建物で、新しく建てられたところに行くと、「なんなんだこれは?」って思うことがありますね。確かにきれいだし、空調も効いているし、使い勝手もいいのかも知れない。でも、そこにいると、知的にわくわくしてくるとか、中を探検したくなるとか、そういう気分には全然ならない。建物の一部を見れば、それだけで全体の構造がどうなっているか、類推できちゃうから。意外なものを求めて中を歩き回りたいという気分にならない。大学の建物を設計するんだったら、真っ先に考えられるべきことは、そこにいる学生たちが知的な高揚感を得ることでしょう。どうしたら、わくわくどきどきするか、それが一番大切なことでしょう。でも、そういうことはまるで考えられてない。今の大学の建物って、一階を見たら、残りの部分が全部わかってしまう。人を探求に誘うような謎も暗がりも全くない。知的な自殺と言う他ないですね。
五十嵐
今の話を聞いて、たとえばヴォーリズとかは、取り壊しなどの話が出ると、建築学会も、保存の要望書みたいなものを出したりするんです。でもそういうときに、どうしても学術的な説明をしてしまう。1900何年に建って、何々様式で、こういう希少な文化的価値があるという、どうしてもそういう説明になるんですけど、今、内田さんがおっしゃったような説明はなされないんですね。
内田
ユーザーとして一番実感するのは声の響きですね。ヴォーリズの建物の中で授業していると、すごく授業がうまく進む。声の反響がすごくよくて、小さい声でしゃべってもはっきり聞こえる。学生も小さい声でしゃべってもよく聞こえるので、声を張らなくてもいい。それに微妙なリバーブがかかるんで、自分のしゃべっていることが、なんとなく賢く聞こえる(笑)。いやいや、あるんですよ、これって。同じリバーブでも、自分がバカみたいに思えるのと、思慮深げに聞こえるのと、違うんです。ヴォーリズはそのことがわかっていたと思うんです。だから、ヴォーリズの建物の中では、授業の深まり方が違う。遮音がどうとか、採光がどうとか、動線がどうとか、そういうことをいろいろ考えて校舎は設計されているんでしょうけれど、声が賢そうに聞こえるかどうかなんて、建築家は誰も考えてくれないんですよ(笑)。でも、校舎の設計で一番先に考えるべきなのは、しゃべると賢そうに聞こえるかどうかですよ(笑)。
光嶋
それはなかなか難しそうだな、建築家としてそれを実現するのは(笑)。
五十嵐
今回は、住宅ですが、普通の住宅とは違って、学びの場である道場がまずある。ということでは、これは道場付きの住宅ではなく、道場に家が付いていると考えたほうがいいんですね。
内田
そうです。
五十嵐
そういうプログラム自体、非常に珍しい。それで、僕が面白いなと思ったのは、自分の博士論文で、新宗教の建築を研究していたのですが、天理教とか金光教とか大本教とか、江戸から明治に出てきたいろんな教団が最初どういうふうに発生して、どういうものをつくっていくかっていう空間の変遷を追ってみたんです。
まずは教祖、つまり教団を始めた人の家にだんだん人が集まっていって、最初は普通の住宅でも何十人かぐらいまでは入る。さらに信者が増えていくと増改築して増やしていく。そうした場所というのは、別に聖なる場所というものではなくて、基本的に人が集まる場所なんです。最初にまず重要なのは、聖なる場所をつくるより、人がいっぱい集まる場所をいかにつくるか。だから、今だって、キリスト教の教会でも、教会とセットでそこにいる牧師さんの住宅を一緒につくるっていうのは、普通にある。内田邸/道場というのは、けっこうそれにも近い。住宅なんだけれども、むしろ集会所であり、学びの場というか、そこは普通の住宅とは違う性格を持って、初期の宗教的な建築と類似しているような性格を感じます。
まずは教祖、つまり教団を始めた人の家にだんだん人が集まっていって、最初は普通の住宅でも何十人かぐらいまでは入る。さらに信者が増えていくと増改築して増やしていく。そうした場所というのは、別に聖なる場所というものではなくて、基本的に人が集まる場所なんです。最初にまず重要なのは、聖なる場所をつくるより、人がいっぱい集まる場所をいかにつくるか。だから、今だって、キリスト教の教会でも、教会とセットでそこにいる牧師さんの住宅を一緒につくるっていうのは、普通にある。内田邸/道場というのは、けっこうそれにも近い。住宅なんだけれども、むしろ集会所であり、学びの場というか、そこは普通の住宅とは違う性格を持って、初期の宗教的な建築と類似しているような性格を感じます。
内田
牧師館って、ありますでしょう。礼拝堂があって、その横に牧師館が付いている。道場はそれと同じ発想なんです。この家は今は「内田邸」ということになってますけれど、そのうち法人化してしまうつもりなんです。僕が個人的に持っていると、僕が死んだときに遺産相続で所有が曖昧になってしまったりすることがある。それがいやなんです。長く合気道の稽古をしていて、道場主が亡くなって、相続した方が「道場みたいな費用対効果の悪い使い方ができない」って、壊して貸しビルにしちゃったとかで二度道場を失っているんです。そうしたトラウマ的経験があるので、個人所有の道場というのはたしかに使い勝手はいいんですけれど、オーナーが亡くなってしまうと大抵潰されてしまう、これだけは避けたい。
道場というのは原理的には半永久的に継続していくべき運動体ですから、私有物のままではまずいと思うんです。だから、どこかの段階で、土地も建物も法人に寄付して、その二階に管理人として住まわせていただいているというかたちにしようと思っているんです。僕が死んじゃったり、奥さんがいなくなったりした後は、この2階部分は全部門人たちの宴会所、集会所になる。プライベートスペースもいろいろ使い道がありそうですから、そういうところは書生や内弟子たちが住み込めばいい。そういうふうに最終的には全体がパブリックなものになるはずなんです。全体の7割5分ぐらいがパブリックとセミパブリックにしてあるのは、そういう意図なんです。
道場というのは原理的には半永久的に継続していくべき運動体ですから、私有物のままではまずいと思うんです。だから、どこかの段階で、土地も建物も法人に寄付して、その二階に管理人として住まわせていただいているというかたちにしようと思っているんです。僕が死んじゃったり、奥さんがいなくなったりした後は、この2階部分は全部門人たちの宴会所、集会所になる。プライベートスペースもいろいろ使い道がありそうですから、そういうところは書生や内弟子たちが住み込めばいい。そういうふうに最終的には全体がパブリックなものになるはずなんです。全体の7割5分ぐらいがパブリックとセミパブリックにしてあるのは、そういう意図なんです。